ホーム > CJLCについて > 出版物 > 日本語・日本文化 > 日本語・日本文化 2011~2005年
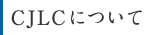
日本語・日本文化 2011~2005年
| 号数 |
発行年 |
カテゴリー |
筆者名 |
題目 |
ページ数 |
| 37 |
2011年3月 |
研究論文 |
松本朋子 |
「いかにも」の歴史的変遷 |
1-23 |
| 研究ノート |
嶋本隆光 |
(続)「知」の意味するもの —形而上的「知」(宗教神秘主義)について— |
25-46 |
| 研究論文 |
奥西峻介 |
双面の者 |
一-三三 |
| 研究ノート |
蔦 清行 |
コソ・已然形研究史抄 |
三五-五七 |
| 36 |
2010年3月 |
研究論文 |
嶋本隆光 |
大川周明と波斯(ペルシア)—続・イスラーム研究への道— |
1-25 |
| 研究論文 |
阪上彩子 |
日本語学習者の話し言葉における不適切な指示詞の使用 |
27-44 |
| 研究ノート |
古川由理子 |
「ほめ」が皮肉や嫌みになる場合 |
45-57 |
| 研究論文 |
柴田芳成 |
カメの報恩・スッポンの報復 |
一-一五 |
| 35 |
2009年3月 |
研究論文 |
坂田達紀 |
小林秀雄批判の文体論的考察(Ⅰ) —中野重治「閏二月二九日」と坂口安吾「教祖の文学」について— |
1-26 |
| 研究論文 |
徐雨棻 |
挨拶表現における“タ”と“ル”両形式の語用論的研究 |
27-48 |
| 研究ノート |
ハルブ・ハサン |
福沢諭吉、ムハンマド・アブドウと西洋文明 —科学主義・合理主義的思考法の受容をめぐって— |
49-66 |
| 研究論文 |
二本松泰子 |
下毛野氏の鷹書 —他流儀のテキストと比較して— |
一-二六 |
| 34 |
2008年3月 |
研究論文 |
嶋本隆光 |
大川周明の宗教研究 —イスラーム研究への道— |
1-22 |
| 研究論文 |
徐雨棻 |
“タ”の表す「発見」について |
23-40 |
| 研究論文 |
ハルブ・ハサン |
福沢諭吉とムハンマド・アブドウの教育思想 |
41-66 |
| 研究論文 |
ムニンタラウォン・シリワン |
「〜てもらう」表現とタイ語における強制性 |
67-87 |
| 33 |
2007年5月 |
研究論文 |
岩男考哲 |
「とする」構文についての覚書 |
1-16 |
| 研究論文 |
仲本康一郎 |
局面解釈とアスペクト現象―生態心理学の観点から― |
17-36 |
| 研究論文 |
ウッディン・エムディ・モニル |
日本語とベンガル語における対称詞の対照研究―親族に関する対象詞を中心に― |
37-54 |
| 研究論文 |
ベルテリ・ジュリオ・アントニオ |
駐日イタリア公使アレッサンドロ・フェ・ドスティアーニ伯爵と外国人内地旅行問題について―明治初期の日伊外交貿易関係を軸に― |
55-81 |
| 研究論文 |
カルモナ・ダニエル・ウイリアム |
徳富蘇峰の歴史確認―ペリーの黒船異変の解釈をめぐって― |
83-108 |
| 研究報告 |
クリモワ・オリガ |
ロシア史料に見るフヴォストフ海軍中尉とダヴィドフ海軍少尉が行った1807年度第2回サハリン遠征とロシア政府の対応 |
109-124 |
| 32 |
2006年5月 |
研究論文 |
五之治昌比呂 |
明治のプラウトゥス―相良常雄『雙児の邂逅』について― |
1-37 |
| 研究論文 |
仲本康一郎 |
属性の意味論と活動の文脈―椅子が荷物になるとき― |
39-61 |
| 研究ノート |
岩男考哲 |
引用構文と「トハ文」 |
63-72 |
| 31 |
2005年5月 |
研究論文 |
中井淳史 |
集古の伝統 尚古系譜―日本歴史考古学の近代― |
1-26 |
| 研究論文 |
ベルテリ・ジュリオ・アントニオ |
宮澤賢治と羅須地人協会―その活動に駆り立てた力について― |
27-61 |
| 研究ノート |
梅村修 |
日本語の要約談話スキル―留学生と日本語母語話者との比較から― |
63-79 |
| 研究ノート |
大塚淳子 |
不同意の表明―日本人大学生の場合― |
81-92 |
このページの先頭に戻る
2025 Center for japanese Language and Culture, Osaka University.
